
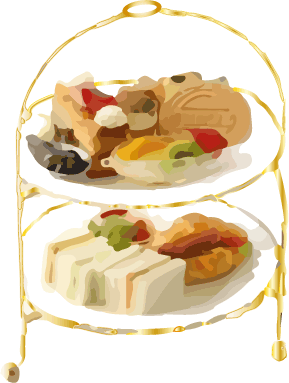
「生麦事件で夷人を斬殺した私」久木村治休述

久木村治休翁(中央)
以下の記事は「神奈川宿古文書の会会報」第41号に掲載された鈴木富雄氏による論稿であり、許可を得て転載させていただきました。
生麦事件後は箝口令がしかれていて、誰も真相を語るものがいなかったのですが、犯人の一人であった久木村治休が94歳(数え年)の時、死を前にして病床で語ったことと伝わっています。70年以上経ってからなので、細かい点は記憶違いがあるようですが、何と言っても、当人が語る内容は非常に鮮烈であり、他のどんな説明より真実味が感じられます。文中にある(筆者注・・・)の部分は、当時の口述筆記をした書き手の方によるものと推察します。
昔の仮名書き、旧漢字など入り混じっています。読みやすくするために、ふりがな、助詞、句読点など、多少手を加えました。(Toshiko)
「資料紹介」 生麦事件の真相
…(略)昭和9年から17年までの約9年にわたり活動した「横浜史料調査委員会」の調査活動史料の中に、生麦事件に関する史料があり、薩摩藩士で、生麦事件で夷人を斬殺した久木村治休翁の口述が昭和11年に雑誌「話」に所載された史料があり、この所載史料を紹介する。
「生麦事件で夷人を斬殺した私」
初めて公表する事件の真相
九十四翁 久木村治休述
昭和十一年四月十一日発行「話」所載
文久二年五月それは私が二十歳の時である、尊王討幕、開港攘夷と國を挙げて狂奔してゐた頃だった、私共の薩摩は討幕へ邁進してゐた。京都から勅使大原重徳卿が東下され、その護衛の大役を命ぜられたのが私の主君島津三郎久光公であった。薩摩藩主久光公は此の重任を無事に果たされ、其年の夏を過ぎて秋風の立ち初むる頃風雲徒らに急を告ぐる京洛の地に帰任する事になった。
時は文久二年八月廿一日(西暦一千八百六十二年九月十四日)の朝まだき、我等一行三百人餘りの大行列は大々名薩摩様の威容に邊を拂いつつ三田の薩摩屋敷を出発し、東海道を西へと上洛の途についたのであった。大井・大森を過ぎる頃から次第に初秋の残暑が身に應へ出した。川崎の宿に休息して昼食をすませた一行は「下に下にツ」の警蹕(けいひつ)の声に路傍に蹲(うずく)まる旅人の中を西へ西へと炎熱の東海道を進んだ。私はその行列の鉄砲組の中に居た。行列の先頭は押足軽、次は挟箱と長柄組、次が鉄砲組である。鉄砲組は二人づ々並んで、赤い毛布で包んだ鉄砲を交替に担ぐのであった。主君の御駕籠はそのずっと後方に多数の御駕籠脇護衛の武士に護られてゐた。
昼下り…今で云ふと午後二時頃…我々一行は武州生麦の里を通行してゐた、行交ふ旅人も此の炎天を避けたか稀であった。
丁度此の頃我々の一行と肥馬にゆるく打たせた四人の夷人とが出会った、当事世にやかましかった黒船の夷人、それが遠乗りにでも行くのであろうか、男三人に女を交へ見事な手捌きでやって来た。
夷人共は私共の行列から見て右側即ち山手側を通って居る、彼等は此の大名行列に行遭って少々ためらってゐるらしい、一行とお互に左行違になって行過ぎようとした。
当事私共薩摩藩士には夷人となると何だか妙に心理が働いたものだった 排他的な気風を多分に有って居た私共は口々につぶやいたものだった。「夷人の癖に馬に乗りやがって…女の分際で…彼奴等商人の分際で…」
「乗り打ちは無礼…冠り物も取るらず…一言の挨拶もせない…」色々と我々は不平を云ったものだった。
四人の一行は馬の足掻きをゆるめて左側を注意に注意を重ねつつ通行した、私共は何となし小さな腹立ちさ、誰に当たらうもない、憤りを感じつ々そのま々通り過ぎるより他に仕方がなかった。私等の先方部隊はそのまヽ無事に通り過ぎた。
此両方が如何に行過ぎたかは従来史家の間に於て問題となっているさうであるが、私ははっきり之を申上げ置く、即ちお互に左行過ぎになったのである、夷人一行はおとなしく通って行った、夷人が馬乗のま々行列先へ踏み込んで来た何のと云うが、それは想像に過ぎない、腫物に触るやうな気で通ったのだ。
飛電一閃(いっせん)夷人を斬る
後方部隊の方で只ならぬどよめきの声があった。私は「すは……」何事が起った事を直覚したので、行列左方脇に飛び出し後を振り返った、私の眼に映した光景は一大事件の惹起した事を明らかに物語ってゐた。強烈な秋の陽光が野芒の如き抜刀にきらめいて居た夥しい人が右往左往し叱咤し怒号しその中に先の夷人が四角八面ににげまどってゐる、さてはあの夷人の狼籍といふ事は直に看取られた。と見る瞬間私の眼の前に一人の夷人が馬上に打伏加減になって左手で脇腹を押へ、右手に手綱を握って野芒の如き抜刀の武士を足蹴にしつ々駆けてきた。「やったなツ…」見れば夷人は左脇腹から夥しい鮮血を流している、誰かに斬られた事は瞭然であった、私は矢庭に腰の愛刀波の平安国二尺六寸五分に手を掛けた、疾風の如く私の前を駆け通る、行列は乱れてサッと左右に道を避けた夷人は私の目の前に迫った、あわや行過ぎようとした、その時遅く彼の時速く私は愛刀を腰の捻りと共に抜き放ちその力を利用してその侭大きく輸を描いて右後方へ払った、右片年打の横一文字だ。「ダッ…ギッヤッ…」愛刀は彼夷人の左脇腹を刀は前腹部から喰ひ込って背後へ後上りにバラリズンと斬られたのだった。二尺六寸五分の大業物の切先が僅かに三寸程か々つた。夷人は私の此の深傷に物凄い叫声をあげてそのまま駆けて行った。人々は此咄嵯の場合だ只抜刀のまヽ呆気にとられてゐる。私は尚も彼の夷人の後を抜刀のまヽ追った。然し残念なから一方は徒歩その間は次第に離れるばかりであった。事実は只是丈である。その間時間にすればほんの数分否私が騒ぎを知ってから夷人を取り逃がす迄は一分もかヽらぬ電光石火の間に行われたのであろう。私が当時の状況から想像し又同僚が其後日に話した事などから推察すると次の様な有様であった事が想像される。
これから先を閲覧するにはログインが必要です。会員登録済の方は右欄の上方からログインをお願いします。新規会員登録(無料)はこちら
