
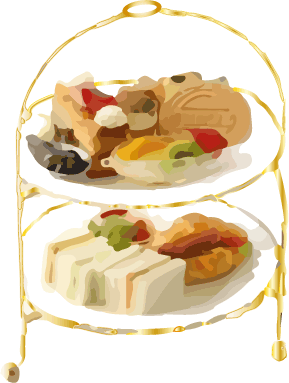
ウィリアム・ウィリス―幕末・明治に多くの日本人を治療した英国人医師 ― Part 2

ウィリアム・ウィリス
Part 1につづき、幕末から明治にかけての日本の激動の時代に、日本の医療と医学の近代化に貢献した心優しき大男、ウィリアム・ウィリスのその後の人生を見ていきたいと思います。
7.横浜軍陣病院 1868年6月~11月30日(慶応4年閏4月~明治元年10月17日)
ウィリスは新政府から要請を受けて、横浜の軍陣病院で戊辰戦争傷病兵の治療に当たることになった。新政府東海道総督府は、1868年6月(慶応4年閏4月)野毛町の旧漢文学校修文館(今の老松中学の地)に横浜軍陣病院を開いた。当初東京に開設しようと考えていたが、ウィルスが江戸と神奈川の副領事に昇進したこと、公使パークスの息子の病気治療中であること、2点を考慮して横浜への開設となった。この病院は日本初の公立外科病院であった。
開設時に7名であった傷病兵の数は9月には207名まで増加し、野毛山下の太田陣屋(今の日ノ出町駅近く)も使用された。負傷者の多くは戦場から横浜へ2、3日掛かって、船で運ばれた。その年の11月に閉院するまで、6か月余り軍陣病院として使われ、その後江戸下谷の津藩邸(藤堂屋敷)に移された。この移転先の病院が、旧幕府の医学所を含めて大病院となり、やがて東京大学医学部へと進展していった。軍陣病院が移転した後、その地には中病院が移転し、1873(明治6)年12月に十全病院となった。これは横浜市立大学医学部付属病院の前身である。
8.東北戦争へ従軍 1868年10月5日~12月28日(慶応4年8月20日~明治元年11月15日)
新政府から、越後の戦傷者の治療のため、ウィリス派遣の要請があった。パークスは直ちに許可を与えたが、「新政府の負傷者だけでなく、捕虜になったものの治療にも当たる。」という条件を付けた。これはウィリスの希望でもあったが、パークスとしては、人道上の理由ばかりでなく、あくまでも局外中立の原則を保持しようとしたからであった。また、新政府は初めウィリスに給料を払うつもりでいたが、出張という形をとることになり、新政府から一切報酬は受けなかった。
ウィリスは1868年10月5日(慶応4年8月20日)に越前藩士25名に護衛されて、江戸を出発し12日掛けて高田へ到着。その後、柏崎、新潟、新発田、会津若松と移動し、寒さと食料の不足に耐えながら、患者の治療と日本人医師の教育に奮闘し、パークスへの報告も怠らなかった。ウィリスからの第一報を受け取って、「まだ旅行が始まってから5日だというのに、これほど興味深い報告に接するのだから、この出張でウィリスがどれほど多くの情報を集めてくれるか、実に楽しみである。」とパークスは述べている。
その後も、ウィリスは忙しい治療の合間に、各地での見聞を覚書にまとめパークスに報告している。その中で、繰り返し触れているのは、治療してきた沢山の負傷兵の中に幕府軍の負傷者がいないという事であった。「これまで私は様々な機会をとらえて、敵方の負傷者にまだ一度も出逢わない失望感を表明してきた。‐中略‐ とりわけ文明諸国は、負傷した敵兵の無差別の殺戮が日本の戦争の特徴であることを知れば、憎悪をつのらせるであろうと言っておいた。そして、私としては、日本政府のヒューマニズムを示す機会に出逢いたいものだと述べておいた。」
新発田(しばた)での治療活動の後、若松行きの要請を受けたが、新政府の要請書には「新政府軍の負傷者ばかりでなく、会津側の負傷者の治療にも当たってもらいたい。」と述べてあった。若松で2週間滞在の間、ウィリスは700名の会津側の負傷者の治療をした。敵味方区別なく人道的な治療ができて、ウィリスの願いが叶った。
ウィリスは3か月にわたる治療の旅を終えて12月28日(11月15日)に江戸へ戻った。踏破した距離は約600マイル(960キロ)にのぼった。600人を自ら治療し、1000人に治療の指導をしたとウィリスは報告している。その内900人が御門の軍隊で、700人が会津兵であった。
これから先を閲覧するにはログインが必要です。会員登録済の方は右欄の上方からログインをお願いします。新規会員登録(無料)はこちら
